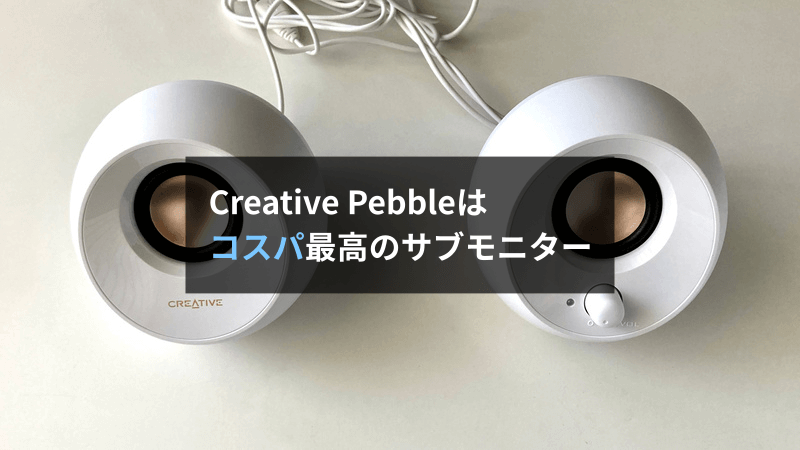音楽制作におけるミキシングの終盤において、「別の環境で確認する」ことは欠かせない工程だ。リスナーが音楽を聴く環境は千差万別であり、ワイヤレスイヤフォン、スマホのスピーカー、ラジカセ的なミニコンポまで幅広い。そのため、GENELECやADAM、Focalといった高品質モニタースピーカー以外の「一般的な環境」に近いスピーカーでのチェックが重要となる。
そんな中で僕が今回導入したのが、Creative Pebbleだ。元々はAmazonや価格.comでベストセラーの、PC向け小型スピーカーだが、これがミックス作業のサブモニターとして非常に役立っている。
あまりにも便利なので、これは全員にオススメしたい!と記事を書くことにした。
目次
スペックと外観

Creative Pebbleは、USB電源で動作するステレオのアクティブスピーカーだ。
- 2インチのフルレンジドライバー
- 周波数特性:100Hz~17kHz
- スピーカーのサイズ:約122mm x 116mm x 115 mm(※片手でつかめるサイズ感)
- USBバスパワー(※電源を取るためだけに使う)
- 3.5 mm AUX入力(※スピーカーから3.5mmステレオケーブルが出ている仕様)
- 出力:総合4.4W RMS(※本体のボリュームをフルテンにすると一般的なモニタースピーカーと同程度の音量が出せる)
外観は丸っこく、デザインが良い。カラーはブラックとホワイトの2色展開。デスク上の雰囲気を壊さず、インテリアとの相性も良い。
Creative Pebbleの2つの魅力
1. フルレンジスピーカーならではの中域特化型サウンド
以前Mix to Mobileのレビュー記事にも書いたことだが、プロの音楽制作のミキシングの現場では、GENELECなどの高級スピーカーだけでなく、SONYのラジカセなど他のスピーカーも使ってミックスを確認することが多い。

それはひとえに、一般リスナーの聴取環境において、ミックスバランスが適切かを判断するためだ。
そのラジカセと同じような役割を果たすことができるのが、このPebbleだ。Pebbleの魅力は、再生できる帯域の狭さにある。周波数特性は次のとおり。
周波数特性:100Hz~17kHz
これじゃキックのローエンドなんて聴こえないし、トップエンドなんてまるで分からない……これでミックスしろなんて言われた日には、どんなエンジニアでもお手上げだろう。しかし、完成しかけのミックスを評価するという用途に限っては、この帯域の狭さがかえって好都合なのだ。
100Hz以下も17kHz以上も出ないような、いわゆる「情報が削られた環境」で再生することで、中域のバランスが浮き彫りになるからだ。
実際、僕もミックス作業ではメインのモニタースピーカーで80%くらい完成させたら、Pebbleに切り替えて確認するようにしている。すると、メインで聴いていたときには気づかなかった、「ボーカルが大きすぎる」とか「ハイハットが大きすぎる」などの問題点がはっきり見えてくる。中域しか出ない環境でミックスをチェックすることの重要性がよく分かる。
PebbleはジェネリックAuratone?
余談だけど、ラジカセと同じような用途で使われる、プロスタジオにおけるサブモニターの定番Auratone 5Cの周波数特性は次のとおり。
80-15,000 Hz
Pebbleと結構近い周波数特性をしていることが分かる。PebbleとAuratone 5Cには、フルレンジスピーカーであるという共通点もある。個人的には、価格が60分の1以下のPebbleのことを“ジェネリックAuratone”と呼びたくなるほどに、便利に使うことができている。
2. 価格がとにかく安い
筆者がPebbleを導入したのは、IK Multimedia iLoud Micro Monitorと迷った末のことだった。iLoud Micro Monitorは素晴らしいスピーカーであることに疑いないが、価格は(モニタースピーカーとしては安価なラインにせよ)数万円はする。
しかしPebbleは、その10分の1以下の予算で購入できてしまう。サブのモニタースピーカーとしての役割に絞れば、性能的にも必要十分。
※初代Pebbleは後継機と違ってDAコンバーターなどがないシンプルなスピーカーなので、製造コストも安いのだと思う。
もちろん、Pebble単体で音楽制作を完結するのは難しいだろう。これはあくまで「メインモニターで全体を整えた後の、ミックスチェック用」として機能するタイプのスピーカーだからである。だからこそ、GENELECやADAMのような高品質モニターと併用するのが前提となる。
音質について
Pebbleはいわゆる「音の良いスピーカー」ではない。耳の肥えた音楽制作者にとっては、安価なコンポやラジカセのスピーカーレベルの音質であり、それ以上でもそれ以下でもない。
ここではあくまでも、サブのモニタースピーカー(ミックスをジャッジするための物差し)として、Pebbleを評価したい。
「100Hz~17kHz」というスペックからも想像はつくが、100Hz以下に存在するキックのロー成分は当然よく聞こえない。しかし、100~250Hzというミックスで混濁しやすい低域は比較的よく分かるという印象だ。仮にこの帯域が濁っているようなミックスの場合、Pebbleで聴けばすぐに低域の整理ができていないことが分かるだろう。
ローエンドが聞こえない分、GENELECやADAMなどの高品質モニタースピーカーで聴くよりも、むしろ100~250Hzの状況に「ダメ出し」するための物差しとしては高性能かもしれない
(より限定的な帯域にフォーカスできるので)。
中域はフルレンジスピーカーだけあってしっかり聞こえてくれる。もしボーカル、スネア、ボーカルなどの音がPebbleできちんとしたバランスで鳴っていなければ、ミックスバランスが良くないことになるので、フェーダーを調整し直す必要がある。そういったラジカセでチェックできるようなチェックポイントを、Pebbleは適切に教えてくれる。
接続方法と使い方
Pebbleのスピーカーからは、3.5mmステレオミニプラグのケーブルが飛び出している。これはノートPCのイヤホンジャックなどに挿して使うことを想定しているためであろう。
普段オーディオインターフェイスやモニターコントローラーから出力させて音楽を聴いているプロ作曲家やDTMerにとっては、少し取り扱いに困る端子かもしれない。
しかし、これをうまく使う方法があるので紹介したい。それは、「フォン×2 ⇔ ステレオミニメス」のケーブルを使うことだ。例えば次のF-Factoryのケーブルを使えば、モニターコントローラーの出力を、そのままPebbleに流すことが可能だ。
オーディオインターフェイス → (TRSフォンケーブルx2) → モニターコントローラー → (F-Factoryのケーブル) → Pebble
と接続することで、モニターコントローラーを経由したオーディオインターフェイスの音を、Pebbleで問題なく聴けることが確認できている。
モニターコントローラー経由で使えば、メインのモニタースピーカーとPebbleをワンタッチで切り替えられるので非常に便利。ちなみに、モニターコントローラーをモノラルモードにした状態で、F-Factoryのケーブルを片方だけ挿せば、1本のスピーカーだけを使ってモノラルで聴くこともできる。これもまたミックスチェックに役立つ小技だ。
僕はかれこれ1年くらい、Mix to Mobileというスマホ転送アプリを使ってミックスのチェックをしている。これも非常に有効であり今でも使っているのだが、いちいちスマホを取り出してアプリを起動するという手間が掛かる。Pebbleを導入してからは、即座にモニター環境を切り替えてミックスを再生できるようになり、作業効率が格段に上がった。
なお、Pebbleの電源はUSBバスパワーで取る仕組みになっているが、ノイズ対策のために僕は別途USB電源アダプターを使って、コンセントから電源を取るようにしている。特にノイズなどが聞こえることはなく、Pebbleを快適に使えている。
開封の儀

こんな箱に入って届く。

フタを開けた図。中央の小さな段ボールには、マニュアルなどが入っている(大したことは書いていない)。

Pebbleとご対面。この簡易包装がコストダウンにつながっていると考えると、好感が持てる。

Rchのスピーカーの背面が、すべてのケーブルの起点となっていることが分かる。ノートPCだとUSB端子は右側が多いからだろう。
まとめ:サブモニターとしては破格のコスパ
Creative Pebbleは、一般的にはPC用スピーカーとして販売されている製品だが、帯域の狭さとフルレンジ構成という理由から、音楽制作における“粗探し用サブモニター”として極めて優秀だ。音楽制作用のアイテムとして捉えるのであれば、価格は驚くほど安く、導入のハードルは限りなく低い。

サブモニター環境を導入したいが、予算が限られている……という人には最初の一台として強くオススメします!